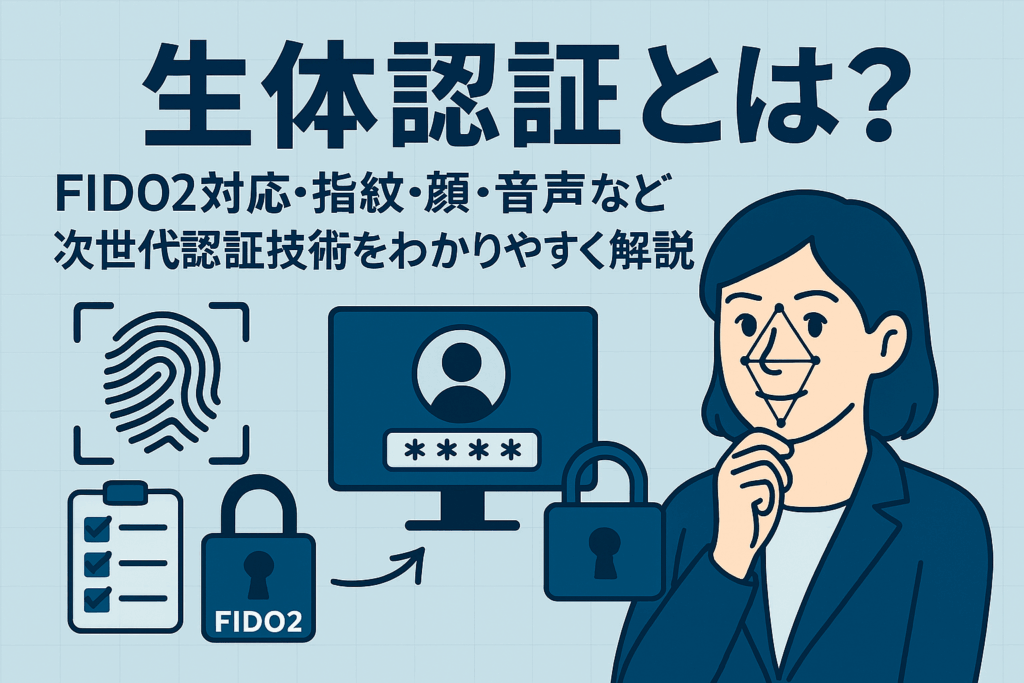スマートフォンの認証には、従来PINコードやパスワードが使われていました。しかし、最近になって指でタッチして指紋認証させたり、顔に向けるだけで認証させたり、手軽な認証機能を搭載したスマートフォンが増えています。これらは、「生体認証」と呼ばれる技術です。指紋や静脈といった、人によって異なる身体的な特徴を認証に使用するので、従来のパスワード認証と比べて盗用のリスクが低いのが大きな特徴です。今回は、この「生体認証」にはどのような種類があるのか解説します。
生体認証規格FIDO2を用いたシングルサインオンが可能なSSO製品についてはこちらをご覧ください。※1
SSOソリューション「KAMOME SSO」
※1 FIDO2とは
パスワードレス認証の普及を推進する業界団体「FIDOアライアンス」によって、2018年に発表された新しい認証技術規格です。ユーザーはパスワードを使わずに、安全かつ簡単に本人認証を行うことが可能になります。
生体認証とは?
生体認証は、人間の身体の特徴を用いて行う認証のことで、別名バイオメトリック(biometric)認証、あるいはバイオメトリクス(biometrics)認証とも呼ばれます。人間の身体を用いて行うところから、特別な準備なしに比較的簡単に利用できる一方で、他人になりすますことが困難であることが特徴です。詳しく見ていきましょう。
生体認証の種類と特徴
生体認証には多くの種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
1.指紋認証
もっともポピュラーな生体認証の方式です。すでに登場してから長い技術のため、他に比べてノウハウが蓄積されているといえるでしょう。一方で、3Dプリンターやゼラチン製の偽造指などによる攻撃リスクが指摘されており、単体での使用ではセキュリティに限界があります。現在は他の認証方式との併用(多要素認証)で補強する傾向が高まっています。
2.顔認証
カメラに顔を向けるだけで照合が行われる、利便性の高い生体認証技術です。近年では、マスクや眼鏡を装着していても認証可能な高精度のシステムも登場しており、スマートフォンやノートパソコンなど、幅広いデバイスに搭載されています。一方で、照明条件や顔の角度によって認証精度が低下することがあり、また双子など極めて顔が似ている場合の判別は依然として課題です。
3.虹彩認証
個人の目の虹彩の高解像度の画像に、パターン認識技術を応用して行われる生体認証方式です。虹彩は遺伝的に個人差があり、生涯を通じてほぼ変化しないため、非常に高い精度を持つとされます。ただし、撮影環境やユーザーの協力(カメラに目を向ける必要性)などの制約があることから、広範な一般用途ではまだ普及が限定的です。
4.静脈認証
静脈を使って本人かどうか判断する技術です。登録しておいた静脈模様と、照合する静脈模様を比べて判断します。表面から複製されにくい点でセキュリティに優れます。主に金融機関や高セキュリティが要求される施設での利用が進んでいます。
5.手のひら静脈認証
静脈認証の一種ですが、静脈認証装置から離れた位置にある手のひらに近赤外線光を照射します。静脈の模様(静脈パターン)から静脈地図を作成して事前に登録します。この静脈パターンは人によってまったく異なるため、登録しておいた静脈パターンと比較照合することで本人認証を行います。
6.声紋認証
声紋認証には、統計学の手法を用います。大量の声のデータを持つ学習データから音声の特徴を認識し、認証対象となる入力音声と、過去に抽出された特徴とを比較しながら、入力された音声が本人かどうか判別して行う認証です。
7.耳介認証
耳介認証は、耳の穴の凹凸の個人差を利用して個人を識別する生体認証技術です。耳の形は複雑に入り組んでおり、個人により形状が比較的異なります。また、体格や相貌に比べれば加齢による変化も少ないため、ここから個人を特定して認証を行います。
8.行動的生体認証
タイピングのリズム、スマホの持ち方、歩き方など、ユーザーの行動パターンを分析して認証します。近年はAIによるリアルタイム行動分析によって本人特定精度が向上しており、継続的認証(ログイン後も監視)に活用されるケースが増加しています。従来の認証を補完する動的なセキュリティ強化策として注目されています。
生体認証のメリットと課題点
メリット
利便性が高い
生体認証は、パスワードやID番号を覚える必要がなく、指をかざす、顔を向けるといった簡単な操作で認証が完了します。これにより、入力の手間を省き、日常的な利用がスムーズになります。スマートフォンのロック解除や決済、オフィス入退室管理など、さまざまな場面で活用されています。
なりすましに強い
指紋、顔、静脈などの生体情報は、原則として人それぞれ固有で、複製や盗用が難しいため、第三者によるなりすましを防ぐのに効果的です。パスワードのように「忘れる・漏洩する」といったリスクもありません。
多要素認証によるセキュリティ強化
近年では、生体認証にパスワードやICカード、スマートフォンなどを組み合わせた「多要素認証(MFA)」の導入が進んでいます。たとえば、「指紋+ICカード」「顔認証+ワンタイムパスワード」のように複数の要素で認証を行うことで、1つの情報が漏洩しても突破されにくくなり、セキュリティを一段と高めることが可能です。
この方式は、金融機関、官公庁、医療機関、企業の重要データへのアクセス管理など、高いセキュリティが求められる現場で特に有効です。
多要素認証についてはこちらの記事をご参照ください。
課題点
生体認証の課題点としては以下が挙げられます。
- 生体情報を抜き取られるリスク
- 身体的変化によって認証不可能になるリスク
- 別人を認証してしまう誤認リスク
生体認証は、自分自身の生体を利用しての認証システムなので、基本的には文字や数字だけのパスワードなどと比べれば安全性は高くなります。しかし、寝ているときに指紋認証されるといった形で、生体自体の特徴や要素を盗用されることもあり、100%安全とは言い切れません。他人を誤認してしまうといった可能性もあるため、現在ではより高いセキュリティ効果を出すために、二段階認証と併用する形で安全性を高めているケースが見られます。 - 100%が保証されるセキュリティはない
生体認証は高い精度でリスクを排除できる認証システムであり、その種類や特徴についてはこれまで見てきた通りですが、生体認証に限らずどんな強力なセキュリティを用意してもハッキングされてしまうことがあるため、100%安心できるセキュリティは存在しないという前提に立って運用を行うべきでしょう。
一方で、生体認証の精度を高め、高い安全性を実現するために、日々新しい技術が開発されており、今後はこの分野の技術はまだまだ飛躍的に進むことが予想されます。 生体認証について理解を深め、従来の方法や二段階認証など他の認証手段と組み合わせることで、より高いセキュリティレベルが実現されるのです。
FIDO2との関係性と今後の役割
FIDO2は、従来主流だったパスワードによる認証手法に代わる、「パスワードレス認証」を世界的に実現するための標準技術として策定されました。この仕組みでは、指紋や顔認証といった生体情報や、物理的なセキュリティキーを用いることで、安全性と利便性の両立を図れます。
従来のパスワード認証には、入力ミスやパスワード忘れだけでなく、同じパスワードの使い回しやフィッシングといった多くのリスクが伴っていました。そのため、不正アクセスによる被害が後を絶たず、より堅牢な認証手法が求められてきました。FIDO2はこうした課題を根本から解決するものです。認証データはユーザーのデバイス(スマートフォンやパソコン、専用トークンなど)の中に安全に保存され、ユーザーがサービスを利用するときも暗号化された形でしかやり取りされません。重要なのは、認証に使われる生体情報(指紋や顔など)は、ユーザーのデバイス内でのみ使用され、外部に送信されることはありません。これにより、万が一サーバーが侵害されても、生体情報の漏洩リスクは極めて低く抑えられます。
また、FIDO2は世界的IT企業が積極的に導入していることから、その信頼性や拡張性は高く評価されています。今後、クラウドサービスや金融、医療、行政など、個人認証の信頼性を強く求められる領域においても、FIDO2の標準化が加速することが期待されています。
さらにFIDO2は、デバイス間でのクロスプラットフォーム対応や、物理キーなどの多様な認証手段との連携もサポートしており、システム担当者やエンドユーザー双方にとって導入・運用しやすい柔軟性も持ち合わせています。このような総合的なメリットから、FIDO2はセキュアな本人認証技術の次世代スタンダードとなりつつあるのです。
まとめ
生体認証は、指紋や顔、静脈などの個人固有の情報を用いるため、第三者による不正アクセスを防ぐ効果が高く、パスワードのように「忘れる」「漏洩する」といったリスクもありません。さらに、日々進化するAI技術やセンサー技術の発展により、生体認証の精度や認識スピードは今後さらに向上すると期待されています。
一方で、生体情報の偽造・盗難、身体的変化による認証エラー、そして誤認によるリスクなど、単独で使用する際の限界も存在します。また、生体情報は一度漏洩すると変更が難しいという性質もあるため、運用には慎重さが求められます。
こうした課題を補う手段としては多要素認証(MFA)が有効です。
このように、生体認証の特性やリスクを正しく理解したうえで、適切な認証手段との組み合わせや運用方針を設計することが、安全性と利便性を両立したセキュリティ体制の構築につながります。
また、かもめエンジニアリングが提供するシングルサインオン&ID管理ソリューションは、生体認証の国際標準規格「FIDO2」への対応を完了しました。
これにより、パスワードレス認証を含むより高度なセキュリティ環境を実現できます。ログインIDやパスワードの管理をより安全かつ効率的に行いたい企業・団体の皆さまは、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
事業・商品・サービスに関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちら
※フリーメールでのお問い合わせは受け付けておりません。